[投稿日] 2012-07-27
▼月とメロン (文春文庫)
[投稿日] 2011-12-18
出版社の社史への批評。
▼内藤湖南への旅
[投稿日] 2011-10-23
12章の支那目録學への關心から店頭で手に取ったら、後半へ行くほど湖南の傳記からも著作からも離れて著者自身の關心する文明論の開陳になってしまってゐる感じ、讀むの止めた。
http://www.fujiwara-shoten.co.jp/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=1217
▼言語哲学への新視角―ウィトゲンシュタインはソシュールを読んだ!
[投稿日] 2011-10-03
副題が「ウィトゲンシュタインはソシュールを読んだ!」とな……ううむ。覗いたら、ちと思ひこみっぽい行論。
http://toshoshimbun.jp/books_newspaper/week_description.php?shinbunno=3069&syosekino=5036
http://reach.acc.senshu-u.ac.jp/Nornir/search.do?type=list01&uid=1204151
▼新たな図書館・図書館史研究―批判的図書館史研究を中心にして
[投稿日] 2011-08-08
第5章 川崎良孝「ウェイン・A.ウィーガンドと図書館史研究―第4世代の牽引者―」
初出: http://hdl.handle.net/2433/139417
第6章 吉田右子・川崎良孝「クリスティン・ポーリーと図書館史研究:プリント・カルチャー史の研究」
初出: http://ci.nii.ac.jp/naid/110008593806
Cf. 川崎「最近の図書館研究の状況 : 批判的図書館(史)研究を中心として」
http://hdl.handle.net/2433/71628
http://toshokanshi-w.blogspot.jp/2011/08/blog-post.html
▼武藤山治と時事新報
[投稿日] 2010-11-17
1.kamiyam 【2010-11-17 18:49】 (削除)
これは、國民會館叢書版(http://www.kokuminkaikan.jp/publishing/index.html)と同一内容なんでしょうかね。ページ数はあまり変わらないようですが。ちなみに以前、図書館のご自由にお持ち帰りくださいコーナーに置いてあったのでパラパラと読みましたが、取り立てて面白くなかった印象だけが残っています。
2.森 【2010-11-18 0:41】 (削除)
古書展で國民會館叢書版を見たけど高くて見送ったのでメモ代りに登録したのです。國民會館叢書ってラインナップを見ただけでも通俗保守論客の顏觸れで期待できませんが、時事新報は社史の無い不幸な新聞社なので基礎文獻とせざるを得ません。註はそれなりに附いてゐたやうですから、文獻を手繰る絲口にはなるかな、と。『三田評論』二〇〇七年四月號「特集 時事新報125年」によれば形式上まだ社は存續してゐるのださうで、慶應の方で研究してくれるとよいのですが。慶應義塾大学法学部政治学科玉井清研究会から〈近代日本政治資料〉と題して戰前マスメディアに關するものばかり十餘點出てゐるやうですが、この教授邊り時事新報をやる氣は無いのでせうか。
3.kamiyam 【2010-11-18 2:29】 (削除)
国民会館のサイト上では在庫切れになっていないようですね。たしかに時事新報は基礎研究がほとんどされてないようだから、せめて文献探索の手助けになるものがほしいところです。慶應の玉井清氏、うーん、時事新報を書誌的にきちんと整理研究するという志向はなさそうな印象ですけど。むしろ可能性があるのは慶應義塾福澤研究センターあたりかなと思うけど、サイトを見る限りそういう計画はないみたいですね。今編纂中という『福沢諭吉辞典』より時事新報の研究をまとめてくれた方がありがたいのですが。
▼書影でたどる関西の出版100 明治・大正・昭和の珍本稀書
[投稿日] 2010-11-16
http://westedit.exblog.jp/
▼文化財の社会史―近現代史と伝統文化の変遷
[投稿日] 2010-10-09
http://d.hatena.ne.jp/jyunku/20101009/p2
▼社会思想史研究 No.34 2010
[投稿日] 2010-09-21
〈特集〉〈社会的なもの〉の概念 再考
目次 http://www.fujiwara-shoten.co.jp/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=1151
▼大衆文化とメディア (叢書 現代のメディアとジャーナリズム)
[投稿日] 2010-09-07
目次 http://www.minervashobo.co.jp/book/b71753.html
▼帰依する世紀末―ドイツ近代の原理主義者群像 (MINERVA歴史叢書クロニカ)
[投稿日] 2010-09-07
目次 http://www.minervashobo.co.jp/book/b48627.html
▼タイポグラフィの基礎―知っておきたい文字とデザインの新教養
[投稿日] 2010-09-05
目次 http://www.idea-mag.com/jp/publication/b031.php
▼想像的なものの人間学
[投稿日] 2010-09-04
http://ehescbook.com/shoseki_shousai/souzou.html
▼てにをは辞典
[投稿日] 2010-08-08
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/tenioha/
▼幽霊記 (新人物往来社文庫)
[投稿日] 2010-06-23
1.森 【2010-06-22 9:0】
表題作「幽霊記 小説・佐々木喜善」 は第98回(1987年下半期)の直木賞候補作の由。同じく三好京三の小説『遠野夢詩人』も1987年初刊だったのは偶然なりや。
2.kamiyam 【2010-06-24 9:0】
私の読書記録コメントに挙げたサイトを作成した人物のブログ記事に「「幽霊記」(副題は小説・佐々木喜善)が発表された昭和62年/1987年ごろは、岩手の辺りから、どんどんと佐々木喜善再評価の熱が上昇していたときでもありました(たぶん)」とあるようですが(中国からcocolog閲覧ができないので、Googleで表示されたとこだけ)、それが本当だとして、「佐々木喜善再評価」ってのが具体的にどんなもので、何をきっかけに起こったものなんでしょうかね。http://www.naokiaward.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/70098-c69b.html
室井康成によると、1980年に遠野市立博物館が作られ、1987年に遠野常民大学が発足するなど、80年代に「遠野市民による『遠野物語』の“読み直し”作業が具体化」したそうですが、それが長尾や三好の創作に影響を与えているのかどうかは?室井康成「『遠野物語』をめぐる“神話”の構築過程—その民俗学史的評価へ向けての予備的考察—」(『総研大文化科学研究』第4号、2008年3月)
http://www.initiati
▼新潮 2010年 07月号 [雑誌]
[投稿日] 2010-06-21
[特集]101年目の遠野物語
目次 http://www.shinchosha.co.jp/shincho/backnumber/20100607/
▼編集者の仕事―本の魂は細部に宿る (新潮新書)
[投稿日] 2010-06-13
淺い、これぁ立ち讀みで十分だ。
▼モダンガールと植民地的近代――東アジアにおける帝国・資本・ジェンダー
[投稿日] 2010-06-05
1.森 【2010-06-04 9:0】
編者の一人である坂元ひろ子著の『連鎖する中国近代の“知”』(研文出版、2009.11)がAmazonに情報無いため登録できぬ。cf. http://www.bk1.jp/product/03235517
2.kamiyam 【2010-06-04 9:0】
昨年からいつになったらAmazonに情報が登録されるのかと思っていましたが、いつまで経ってもされませんね。研文出版や柏書房はデータがごそっと抜け落ちているようです。売れない本は必要ないということでしょうか。
3.ekura 【2010-06-06 9:0】
Amazonと取引していないということではないでしょうか。岩田書院さんもたしか新刊ニュースの裏便りで言ってたと思いますが、抜かれるマージンがけっこう割高で、何千部も売れれば得になりますけど、何十冊単位でしか売れないちっちゃいとこだとキツいようです。
4.森 【2010-06-08 9:0】
やはりAmazon獨占状態はよくないなあ……などと言っても、部屋滿杯の藏書のうち新刊の定價で買った本が本棚一段分程も無い古本者の言葉では空しい。
目次 http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0253060/top.html
▼戦時統制とジャーナリズム―1940年代メディア史
[投稿日] 2010-05-25
ほとんどが笠信太郎論。あと、誤植ひどい。
http://www.shuppan.jp/bukai12/360-19402010614.html
目次 http://www.showado-kyoto.jp/book/b96885.html
▼出版の魂―新潮社をつくった男・佐藤義亮
[投稿日] 2010-04-13
偉人傳だな。












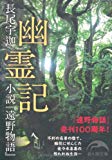
![新潮 2010年 07月号 [雑誌]](http://bookish.s1007.xrea.com/x/wp/wp-content/uploads/2018/12/41QfXrJGWuL._SL160_.jpg)



