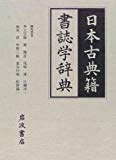[投稿日] 2010-12-11
▼戦時グラフ雑誌の宣伝戦―十五年戦争下の「日本」イメージ (越境する近代)
[投稿日] 2009-10-29
[最終更新] 2014-09-29
▼書林の眺望 伝統中国の書物世界
[投稿日] 2011-07-27
おほむね版本學に屬し、目録學と言へるのは「四部分類の成立」のみ。「編目談余」は目録編纂に版本學の知識が要ることを説くものだし、「『千頃堂書目』と『明史芸文志』稿」も對象は目録書だが研究法は版本學、或いは鈔本(寫本)だから校勘學か。「内藤湖南蔵本『文史校讎通義』記略」も成立過程を探った本文批判。
目次 http://d.hatena.ne.jp/ginzburg/20061112/1163323547
▼知の座標―中国目録学 (白帝社アジア史選書)
[投稿日] 2011-06-26
四部分類を成立せしめた「史部」が、ポイントになってゐる。川勝義雄『中国人の歴史意識』と併讀すること。著者は觸れてないが、「六經皆史」と斷じた章學誠の『文史通義』につなげられるだらう。つまり、本書と同樣にして新たな支那史學史が書かれることが望ましいが、なぜか目録學關係の著作者は文學研究者ばかりみたいで期待できない。
井波陵一「六部から四部へ――分類法の変化が意味するもの」(冨谷至編『漢字の中国文化』昭和堂、2009.4)に竝んで補ふ所あり。
井波陵一編『漢籍目録を読む』(〈東方學資料叢刊〉京都大學人文科學研究所附屬漢字情報研究センター、2004.3)は、内題では副題に「――実習(カード作成・データ入力)のために」とある通り、圖書館司書向け講習用の教本册子に留まり、讀むに及ばない。
▼読むと書く―井筒俊彦エッセイ集
[投稿日] 2009-11-24
▼思いで草 (第二集)
[投稿日] 2016-04-23
「非売品」、國會圖書館所藏無し。
序文(尾崎芳治)
堀江保蔵先生
岡部利良先生
田杉 競先生
出口勇蔵先生
山岡亮一先生
島 恭彦先生
編者のあとがき(木崎喜代治)
書名中「第二集」は、函・本體の背文字では丸括弧が附かない。
奧附「発行者」は、經濟學部長の尾崎でも編者の木崎でもなく「代表者 伊東光晴」。
創立七十周年記念。堀江・岡部の分は『経済論叢』既出だが「形式の統一のための若干の修正を加えて、本書に再掲」(p.231)。
瀧川事件や上野文庫に關する回想を含む。
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN13457004
▼創立五十年記念 思いで草
[投稿日] 2016-04-23
「創立五十年記念」は標題紙にのみ添へられてゐる。「非売品」、國會圖書館所藏無し。
『京都大学七十年史』(一九六七年)との重複もあって學部五十年史を斷念し、そのために録音してゐたインタビューを代りに刊行した。
「序」堀江英一
はしがき
高田保馬先生の巻
本庄栄治郎先生の巻
小島昌太郎先生の巻
作田荘一先生の巻
石川興二先生の巻
蜷川虎三先生の巻
静田 均先生の巻
豊崎 稔先生の巻
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN13457004
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I054641506-00
▼京都書肆変遷史―出版文化の源流
[投稿日] 2009-10-30
▼身体としての書物 (Pieria Books)
[投稿日] 2009-10-29
目次 http://www.cafecreole.net/onbooks/
▼文献日本語学
[投稿日] 2009-11-25
目次 http://www.minatonohito.jp/products/093_02.html
▼振仮名の歴史 (集英社新書)
[投稿日] 2010-09-12
著者のマニアックな良さが新書判だと出せなかったやうで、ガッカリ。この程度が當今の新書に求められる「わかりやすさ」なのかも。
チト驚いた豆知識をメモ。「『夜想』などの雑誌を出版していたペヨトル工房(一九七九?二〇〇〇)を主宰していた今野裕一は筆者の実兄であるが、筆者も「北野真弓」などという名前を使って『夜想』の編集の手伝いめいたことを少しの間していた」(p.147)。それだから『消された漱石』はあんな凝った版面設計だったのか?
▼『遠野物語』100年の記憶――佐々木喜善と仙台――
[投稿日] 2016-07-08
國會圖書館所藏無し。
寄稿者は山折哲雄、内藤正敏、佐々木徳夫、熊谷達也、石井正己。
企劃展圖録。
http://web.archive.org/web/20100123052027/http://www.lit.city.sendai.jp/exhibition_2.html
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB01110570
▼伊東俊太郎著作集〈第10巻〉比較思想
[投稿日] 2009-11-18
▼テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ
[投稿日] 2010-12-19
▼操觚字訣―同訓異義辞典 (1980年)
[投稿日] 2011-09-04
須原屋書店明治三十九年十月再版→明治四十年十一月七版を入手。
伊藤善韶(東所)序が寶暦十三(一七六三)年、刊本が出たのはやっと明治十二年(~十八年)だが、五十音順排列は稿本通りだったのだらうか。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/902815/418
▼忘れ得ぬ国文学者たち―并、憶ひ出の明治大正 (1973年)
[投稿日] 2011-04-29
國文學研究史の背景としては使へる。
著者が沼波瓊音が大好きなのはよく解ったが、あまり魅力を感じない。同樣に岩本素白も言はれるほどいいと思はぬのはこちとら散文的な朴念仁だから仕方無いのかしれんが、しかし紹介されてゐる岩本書翰はなかなか讀みたくなる文章なので、全部を收録するといふ『近世日本文学管見』を探すとしよう。それにしても、著者の文章はその敬慕する文筆家たちの影響がまるで感じられず、平易ではあるが可もなく不可もなく、凡庸な文體なのは不思議。ほんの稀に凝った用字が出るくらゐ。福澤諭吉に倣ったわけなのか? 纔かなこだはりであった歴史的假名遣も歿後の新版では現代假名遣ひにされてしまったので、敢へて舊版を探してゐた。
1.kamiyam 【2011-05-07 3:59】 (削除)
私は伊藤の文体は結構好みです。まさに平易かつ凡庸なところがいいなあと。
2.森 【2011-05-07 14:48】 (削除)
いやあ、惡いとも嫌ひとも思ひませんが、特徴の無いものを好むのは難しい。森銑三みたいに、端正なやうでもあからさまに整へた書きぶりだと文體の特徴が掴めるんですが。フランソワ・ジュリアン『無味礼賛』でも讀んだら參考になるかしらん。
目次(新版) http://www.yubun-shoin.co.jp/book/book_detail/4-8421-0007-9.html
▼児戯生涯―一読書人の七十年 (汲古選書 (15))
[投稿日] 2010-11-29
▼大衆文學論
[投稿日] 2015-04-19
著者本名は相良徳三。「卷頭の「大衆文學論」は、[……]昭和十六年に雜誌「文藝情報」に連載したもの」(「跋」p.332)。尾崎秀樹『大衆文学論』所收「伊集院斉論」を見よ。
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1069499
一九三五年創刊『懸賞界』→一九四〇年(四月?)改題『文藝情報』は、投稿雜誌の末流として曾て曾根博義らも注目せる所にて、刊行圖書には懸賞目當ての投稿青年に向けた文章・文藝指南の通俗書多く、日本文藝研究會編『文藝作り方講座』(櫻華社、一九三六~)上中下篇は中々の執筆陣。三輪健太郎『短篇小説の作法と解剖 プロツト・ブツク』(櫻華社出版部、一九四一年五月五版)を二〇一一年十二月に購入せしことあり。
Cf. http://www.geocities.jp/moonymoonman/i/bungeijouhou.txt
▼住谷天来と住谷悦治―非戦論・平和論―
[投稿日] 2016-10-02
國會圖書館所藏無し。「頒布価格」は「会員外一册一、五〇〇円」。發行所みやま文庫は「群馬県立図書館内」。
住谷一彦「住谷天来への支店――非戦平和の思想像――」
住谷一彦「住谷天来と父・悦治」
手島仁「解説 住谷天来」
手島仁「解説 住谷悦治」
森村方子「住谷文庫と群馬県立図書館」
年表・住谷天来
年表・住谷悦治
住谷家略系譜
著作目録・住谷天来
著作目録・住谷悦治
住谷磬「あとがき」
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA31888119
▼科学革命の歴史構造〈下〉 (講談社学術文庫)
[投稿日] 2010-09-04
數學史が主だが、文獻學の影響を重視してゐる。