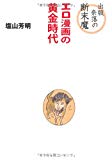[投稿日] 2011-01-14
▼母校早稲田
[投稿日] 2015-08-22
非賣品。標題紙でのみ書名に「喜多壮一郎遺稿集」と冠し「母校 早稲田」と二語の間をやや空ける。
早稻田大學私史を試みたもの、師友回想などを插む。
國會圖書館所藏無し。
題字・中村宗雄
序に代えて――わたくしの立場――
目次
第一章 早稲田学園の誕生――理想と苦しみ――
第二章 学園における最初の紛争――法律科の内紛――
第三章 早稲田「三博士」と初期の卒業生群像
第四章 雄弁会の歴史
第五章 校友会・講義録・寄宿舍
第六章 「早稲田大学」の学生々活
第七章 早稲田騒動
第八章 科外講演
第九章 なつかしの思い出
あとがき 酒枝義旗
おわりに 甲野善勇
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA39062032
▼動くジャーナリズム
[投稿日] 2016-04-30
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1230178?tocOpened=1
裸本。目次にのみ「――アメリカ篇――」の副題あり。裏表紙には“The Story of American Journalism”と英題あり。「自序」に曰く「本書は元來、日本新聞協會附屬新聞學院に於て講義する資料として計劃したものであるが、結局、大衆向に筆が滑つてしまつた」(p.3)。
▼図書館情報学ハンドブック
[投稿日] 2013-05-01
第2版。
▼形容詞の意味・用法の記述的研究 (国立国語研究所報告 44)
[投稿日] 2011-01-08
▼国際日本文化研究センター25 年史[資料編 1987-2012]
[投稿日] 2016-07-08
書名は標題紙に據る。背文字・奧附では副題は「―資料編―」。
「編集後記」の「25年史編纂室長」は瀧井一博。奧附「編集協力」に「株式会社エトレ」とあり、同社サイト周年事業室の「これまでの実績」には「沿革としての歴史記述は、別途「物語編」として出版」とあるも、その書名では見つからぬ。察するに、猪木武徳・小松和彦・白幡洋三郎・瀧井一博編『新・日本学誕生 国際日本文化研究センターの25年』(角川学芸出版、二〇一二年十二月)のことか?
http://shunen.etre.co.jp/works/2012/03/10/120310-kokusainihon/
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB09793069
▼澁谷近世 國學院大學近世文学会会報 第二十一号「朝倉治彦先生追悼特集」
[投稿日] 2015-04-24
或る種の書物人の代表としての朝倉治彦の名が氣に懸ってゐたため碌に追悼文も出ないのは惜しく念ってゐたが、辛うじて大學の縁でこのやうな記録が纏まったのは、有り難い。「経歴と業績年譜」(pp.10-24)は朝倉自身の原稿に基づいて生前に補正を進めてゐたものとのこと。
卷末「『近世文学会会報』既刊号細目(第一~二十号)」のみならず、小島瓔禮「明日へのために――國學院大學近世文学会」のこと――」、中村正明「『澁谷近世』と朝倉治彦先生」等のあることで、ちゃうど二十號までの雜誌と研究會の來歴を振り返る號となった感がある。
目次 http://kinbun.jugem.jp/?eid=1185
▼なぜ言語があるのか (土屋俊 言語・哲学コレクション第4巻) (土屋俊言語・哲学コレクション 第 4巻)
[投稿日] 2009-11-25
▼連鎖する中国近代の“知”
[投稿日] 2012-07-27
▼神保町「二階世界」巡り及ビ其ノ他
[投稿日] 2009-11-09
▼ことばの哲学 (1983年) (現代哲学選書〈4〉)
[投稿日] 2010-07-29
一九七二年刊(学文社發賣)の新版。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kisoron1954/11/4/11_4_181/_article/-char/ja/
▼本日記
[投稿日] 2010-08-07
この本を離れた一般論になるが、腹立日記が日記の藝のうちだと勘違ひしてゐるのは賢しらな人には多い、のかも。私憤に私憤を同調させ得る讀者には迎へられるにせよ、飮食店で店員に威丈高に怒鳴る客の横に置かれたやうな嫌な氣分も起こる。特に、本とあまり關はり無い不平不滿を聞かされると、さうだ。しかし本への批判なら怒りを丸出しにして良いのかといふと、やはりそこにも藝はあって貰ひたい。一體インテリの讀書家は陰鬱で神經質なものではあるが、小谷野敦らが時折見せるヒステリックなクレーマーぶりには似たくないものだ。
私生活はどうでもよいが、古本の蘊蓄を語ってゐるところは良い。
▼歴史学のすすめ (1973年) (学問のすすめ〈11〉)
[投稿日] 2010-10-02
▼現代歴史学入門 (1965年)
[投稿日] 2010-10-16
III「歴史学の方法(2)――史料の批判と解釈――」―§2.「史料の理解」(堀越孝一)が目當て。科學認識論に踏み込んでゐるのは歴史學者としては珍しい。コリングウッド批判も妥當だらう。
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3049118
▼明治文化研究会と明治憲法―宮武外骨・尾佐竹猛・吉野作造
[投稿日] 2009-10-29
題材の割に今一つ。構成や文章を練り込めばもっと面白くなるのに。
▼法のことば/詩のことば―ヤーコプ・グリムの思想史
[投稿日] 2009-10-29
▼出版奈落の断末魔―エロ漫画の黄金時代
[投稿日] 2009-10-30
▼イデアと制度
[投稿日] 2009-11-27
第6章 教養―図書館における書物の置き方と王子の教育について
第7章 批評―人文科学の確実性、あるいは箇条書きに宿るイデアについて
目次 http://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0589-0.html
▼佐幕派論議
[投稿日] 2010-08-07
▼文学的記憶・一九四〇年前後―昭和期文学と戦争の記憶
[投稿日] 2009-10-29
目次 http://honto.jp/netstore/pd-contents_0602735661.html