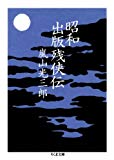[投稿日] 2011-03-26
▼ブックビジネス2.0 - ウェブ時代の新しい本の生態系
[投稿日] 2010-08-07
▼私のあとがき帖 (1980年)
[投稿日] 2011-01-28
▼集團主義の文藝
[投稿日] 2015-10-09
目次に無いが卷末に跋文「著者の言葉」あり、なかなか勇んでゐる。曰く、「個人主義文藝と對立し、それを國家主義文藝の中へ發展的に解消せしめるための指導勢力を 形成すべき任務が、集團主義の文藝に課せられてゐる。」(p.463-464)「著者は本年一月「經國文藝の會」に於て陸軍省鈴木少佐の高見に接し、共感を禁じ得なかつた。革新日本に於ける皇軍の不變の推進力(最近の「利潤統制」の如きはその第一歩である)の中に歴史的必然を認識する著者にとつては、集團主義文藝論の勝利は確信中の確信である」(p.464)。明らかにソヴィエト・ロシア産理論に依據したプロレタリア文學盛期の舊論を收めながら特に伏字もなく出版し得たのはこの鈴木庫三への世辭等が煙幕になってお目こぼしされたのではあるまいか、などと邪推したくなってしまふ。
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1071821?tocOpened=1
▼日々是趣味のひと
[投稿日] 2016-05-29
「刊行 岡澤貞行偲ぶ会」「発行所 荻生書房」。
齋藤昌三に師事した愛書家のエッセイと追悼文十八篇。武井武雄作藏書票等を貼附するため古書價は數千圓する。
▼近世庶民文化 第廿九號
[投稿日] 2016-11-06
表紙では「第廿九號」、目次では「第二十九號」と表記。「非賣品・會員以外に頒布せず」。
宮武外骨先生追悼
木村毅「宮武外骨翁」pp.53-55
柳田泉「外骨先生と私」pp.55-59
齋藤昌三「浮世繪から古川柳へ」pp.60-62
▼書痴半代記 (ウェッジ文庫)
[投稿日] 2010-09-05
「うたごえ運動」の關鑑子が關如來(柯公全集編者)の娘だったとは……と、どうでもいい瑣末事を拾って悦ぶのみ。だって記述が淡泊で物足りないんだもの。所詮は詩人の隨筆だからか(←偏見)。
▼続読書清興―岩倉規夫遺稿集
[投稿日] 2010-07-29
http://www.kyuko.asia/book/b9278.html
▼明治版画史
[投稿日] 2009-11-09
▼近代文学論文必携 (1963年)
[投稿日] 2010-12-12
▼岩波文庫の80年 (岩波文庫)
[投稿日] 2010-09-06
▼歴史学事典〈第11巻〉宗教と学問
[投稿日] 2014-01-02
平成21年5月31日初版2刷、送料入れて二千五十圓と定價の八分の一程、桁外れの廉價で入手。
「責任編集岸本美緒」だが、岸本執筆分は目録學を説いた「図書分類法(中国の)」と「封建論」との二項のみ、支那思想史關係は小島毅擔當が多い。執筆者索引を備へるのは弘文堂の事典の特色ではないか。
「書評」(小森陽一)など、折角の面白さうな立項が執筆者に人を得なかったため不成功となったものもあるが、「項目分類目次」を眺めてゐるだけで興が湧き、それからそれへと引きたくなる。
あと手許に欲しい卷は、『3 かたちとしるし』『15 コミュニケーション』『5 歴史家とその作品』『6 歴史学の方法』あたりだが、なかなか貧書生には手が出ない。
http://web.archive.org/web/http://www.koubundou.co.jp/subsite/21041/index.html
http://www.koubundou.co.jp/book/b156922.html
▼ドイツ史学思想史研究 (1976年)
[投稿日] 2010-09-11
期待したコゼレックらの概念史・社會史についてはこの本が取り上げた後の時代に屬すゆゑ論及されてなかった。概觀としてはよく調べてあるものの、對立する二項を取り出したところで論が終ってしまふのでもっと突っ込んだ考察が欲しい。これをちゃんと「思想」史とするには、哲學的訓練を經た上で諸概念の歴史的關係の内實を論理に即して考へ詰める作業が要る。
本書刊行以降に發表された關聯論文として下記あり。
▼「ドロイゼンの「史学論」(一八五七)におけるGeschichteの問題 」名古屋大学教養部『紀要 A (人文科学・社会科学)』第23輯 、一九七九年三月
▼「ホイシにおける「歴史主義の危機」の問題 」名古屋大学教養部『紀要 A (人文科学・社会科学)』第25輯 、一九八一年九月
▼「戦間期ヨ-ロッパ歴史思想における「危機」の問題」名古屋大学教養部『紀要 A (人文科学・社会科学)』第30輯 、一九八六年二月
▼「『歴史的基礎概念事典』――〈Geschichte〉の項――」日本大学文理学部『學叢』第43號(昭和62年度)一九八七年十二月「特集 辞書・事典」
▼昭和出版残侠伝 (ちくま文庫)
[投稿日] 2011-04-03
文章が良くない。輕薄體としても、だ。
▼新たな図書館・図書館史研究―批判的図書館史研究を中心にして
[投稿日] 2011-08-08
第5章 川崎良孝「ウェイン・A.ウィーガンドと図書館史研究―第4世代の牽引者―」
初出: http://hdl.handle.net/2433/139417
第6章 吉田右子・川崎良孝「クリスティン・ポーリーと図書館史研究:プリント・カルチャー史の研究」
初出: http://ci.nii.ac.jp/naid/110008593806
Cf. 川崎「最近の図書館研究の状況 : 批判的図書館(史)研究を中心として」
http://hdl.handle.net/2433/71628
http://toshokanshi-w.blogspot.jp/2011/08/blog-post.html
▼言語哲学への新視角―ウィトゲンシュタインはソシュールを読んだ!
[投稿日] 2011-10-03
副題が「ウィトゲンシュタインはソシュールを読んだ!」とな……ううむ。覗いたら、ちと思ひこみっぽい行論。
http://toshoshimbun.jp/books_newspaper/week_description.php?shinbunno=3069&syosekino=5036
http://reach.acc.senshu-u.ac.jp/Nornir/search.do?type=list01&uid=1204151
▼書物の周圍 第三年第一・二號
[投稿日] 2016-05-04
標題紙・奧附では「第三年第一、二號」と中黒でなく讀點で表記。
奧附p.40に「本誌は當分春秋二回發行。/左の通り實費頒布いたします。/頒價金四拾錢 送料四錢」と記すも、本號限りにて終刊。
http://id.ndl.go.jp/bib/000000011811
▼書物の周圍 第二年第一號
[投稿日] 2016-05-04
「くにたち本の會」は東京商科大學附屬圖書館内、國立市はまだ無いが東京府北多摩郡谷保村字國立。「非賣品」。
奧附ページ(p.42)に「第一年總目次」あり。全五册の總目次は『書物関係雑誌細目集覧 二』を見よ。
ゆまに書房〈書誌書目シリーズ〉にて一九九三年複刻。
http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN0009808X
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN09578810
▼孤高 国語学者大野晋の生涯
[投稿日] 2009-10-30
▼川田順遺稿集香魂 (1969年)
[投稿日] 2010-12-26