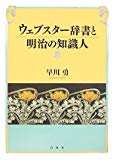[投稿日] 2011-01-21
▼図書館情報学用語辞典
[投稿日] 2010-08-28
第2版二〇〇二年八月、第3版二〇〇七年十二月、第4版二〇一三年十二月刊。
https://kotobank.jp/dictionary/tosyokan/
▼季刊 子どもの本棚 21「特集 子どもの本の研究をふかめるために」
[投稿日] 2015-08-16
奧附刊記は「昭和五二年八月発行」とのみありて日附無し。
「子どもの本の研究」と稱し、兒童文學研究から出ようとして、なほ離れ切れずにゐるところが問題。卷頭「座談会 子どもの本の研究をどうすすめるか」にて最初に問題提起する鳥越信曰く、「児童図書のなかには文学以外のジャンルもあるからという、単純なものではないんです。ゴーリキイは、理科的なものまで含めて全部児童文学と呼んでいいと言っているくらいですから、子どもの本はすべて児童文学だと、ぼくらも考えているのです」――ウン、まづその文學への拘泥を脱却しなくっちゃ。そして心理學や教育學に助力を仰ぐ前に、本そのものを研究する書誌學・書物史に開眼すべし。
▼季刊 日本思想史 NO.20「特集 懐徳堂の思想」
[投稿日] 2016-11-12
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/7949992?tocOpened=1
▼季刊日本思想史 no.72特集:近代日本と宗教学
[投稿日] 2009-12-18
「特集 近代日本と宗教学−学知をめぐるナラトロジー」
http://www.perikansha.co.jp/Search.cgi?mode=SHOW&code=1000001470
▼百科事典の365日
[投稿日] 2016-08-28
「〔非売品〕」「セールス資料」。新書判、本文382ページ。國會圖書館所藏無し、CiNii所藏無し。
「はしがき」に曰く、「この本は世界大百科事典のセールスマンのために作ったものです。」「拡販のための材料として,いままでにアブリッジ版とか「しらべる」とかいったものが作られて参りました。」「セールス・トークはむずかしいもの,世界大百科への導入はむずかしいものと,よく考えられておりますが,そういった方がたは,ぜひこの本で話のいとぐちを見つけてください」。
小林祥一郎に據れば「1966年には「ほるぷ」その他の有力販売会社を統括し、その活動を支援するために「日本教育産業センター」(略称EIC)が設立された」(#)。一九七二年一月に下中邦彦が社長就任、八月に平凡社教育産業センターと改稱。
# http://www.shinjuku-shobo.co.jp/column/data/Kobayashi/008.html
http://www.shinjuku-shobo.co.jp/column/data/Kobayashi/006.html
▼日本文学 1964年3月号
[投稿日] 2015-05-09
橋本寛之・小島輝正・平林一・土橋寛・飛鳥井雅道・猪野謙二(司會)「《座談会》 批評と研究」
杉山康彦「論文紹介 鷹津義彦氏「日本文学史家の史観と方法」大谷短期大学紀要」
高田衛「《書評》 松田 修著『日本近世文学の成立――異端の系譜――』」
ほか
▼日本文学 一九六〇年二月号
[投稿日] 2016-07-31
祖父江昭二・広末保・西郷信綱・花田清輝「座談会 柳田国男をめぐって」
高田衛「文学がわからないということ」
日本文学ニュースNo.49「悼む・風巻景次郎氏」
西郷信綱「一つの決定的瞬間について――風巻先生のこと――」
丸山静「風巻景次郎先生」
ほか
「雑誌記事索引」では二ページ以下の記事は拾ってない。
https://ndlopac.ndl.go.jp/F/1942I4JG35P1BFL9ALUAUBH8974LPMA2XN9VBV966TESVFIKBT-06889?func=z103-set&doc_number=011584325
▼日本史研究者辞典
[投稿日] 2010-08-04
ほぼ履歴の羅列に終始、手堅くはあるが、面白味ある記述は見られない。專門研究者でなくとも日本史絡みの著述がある人物ならば色々拾ってあるのが取り柄だが、大學等の組織に所屬しない人だとかういふ公文書的記述ではうまく仕事が掴めまい。
http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b33075.html
http://sakuin.g.hatena.ne.jp/hitobito/20071103
▼日本歴史 2000年9月号(第628号)「小特集〈近代文書論〉」
[投稿日] 2016-08-27
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/7910685?tocOpened=1
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I002495526-00
▼民主文学 1975年4月号
[投稿日] 2015-04-25
「特集=江口渙追悼」
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/7973533?tocOpened=1
▼文学研究における継承と断絶―関西支部草創期から見返す (いずみブックレット)
[投稿日] 2011-04-26
企劃者の「近年の研究状況は、[……]現下の立脚点になった「近過去」の積み重ねにあまりにも冷淡」(p.2)といふ問題提起は結構なのだが、シンポジウムがまるで討論になってない感想會なのはいつものことながら殘念、但し前田愛のエピソードが拾へる所は面白い。パネリスト二名のうち平岡敏夫「文学史研究における継承と断絶」は過去の自文の引用ばかり、歩一歩を進めて貰ひたいのだが(特に「『明治文学史』研究」で)老齡には酷か。谷沢永一「文学研究の発想」の方は、既發表との重複も多いが流石にハナシはうまい。方法論論爭の背景にあった三好行雄の對小田切秀雄批判の代理戰爭といふ面については小谷野敦『現代文学論争』(2010.10)が特筆してゐたが、先驅けてここで谷澤本人が明言してゐるのであり、これを參照すべきだった。しかし谷澤自身が「最後にものをいうのは事実です」と約言してしまひ(p.22)、それを「最後にものを言うのは事実だ」とのみ受け取る(p.47浅野洋發言)やうでは、論爭の意義を矮小化した「継承」になる。やはり改めて「方法」について前田愛からの批判をも含めて再考すべきであり、でなくては故人も浮かばれまい。
目次 http://www.izumipb.co.jp/izumi/modules/bmc/detail.php?book_id=10062
▼ウェブスター辞書と明治の知識人
[投稿日] 2009-11-13
▼明治文學
[投稿日] 2015-06-27
奥付には「明治文學合本」題扉には「明治文學 第壹卷」と記し第一輯より第四輯までを收めるが、第五輯以下續刊されなかったので第貳卷も無く、これで全號揃ひである。新たに藤村作「序」を附す。各輯細目は『現代日本文芸総覧 補巻』を見よ。
▼中国と台湾の社会学史
[投稿日] 2015-08-15
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN12602673
▼文學評論
[投稿日] 2016-06-24
裸本。舊藏印「池田藏書」。
全100篇に再編した上での卷末「INDEX」pp.370-353の充實に、編輯者としての春山の才覺が窺はれる。
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1214062?tocOpened=1
▼近代文学研究叢書〈第31巻〉 (1970年)
[投稿日] 2011-01-28
「訂正版」一九七〇年三月刊。一九六九年刊が初版らしいが國會圖書館無し、未見。
内田魯庵 アーネスト・サトウ 齋藤秀三郎 宇田川文海 内村鑑三
http://www.kikuchi2.com/moku/showa.html
▼アカデミック・ライブラリー 郷土史と近代日本
[投稿日] 2009-10-29
[最終更新] 2014-07-09
目次 http://asios-blog.seesaa.net/article/145140870.html
▼國語問題と國語教育
[投稿日] 2015-09-27
國會圖書館所藏無し。
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN08631088
中教出版と改稱した同じ版元より増訂版(一九六一年十月)あれど、「六」~「一一」は削除され、代りに「五 スターリン 「言語學におけるマルクス主義」に關して」「八 「かなづかひ」の原理」「九 利用者の立場から見た「送りがなのつけ方」同追記」「十 漢字政策上の諸問題」「十四 國語政策のための基礎的研究について」「十五 國語國字政策論の盲點」六篇を加へたものなので、章數は増減無く、差し替へ分はこの舊版にのみ見るを得。うち六~一〇「國語科學習指導要領試案」は後に石井庄司編『時枝誠記国語教育論集 I』(〈国語教育名著選集〉明治書院、一九八四)にも再録。
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN09750876
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2495371?tocOpened=1
http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/TOKIEDA/K_K_Chukyo.html
▼月刊島民 中之島 2015年5月号(Vol.82)
[投稿日] 2015-05-01
16ページのフリー・ペーパー。特輯「中之島図書館はすごかった。」
インタビュー記事「ココがすごい/本と人 「書を司る」ということ。」中、「ビジネス支援課/司書 小笠原弘之さん」(p.6)の末尾に曰く――「レファレンスでお受けする質問は、確かにより回答が難しいものが多いです。一方で、図書館や司書の質を向上させることにもなる。開架数を増やして自分で見つけ出してもらうのが図書館の醍醐味ですが、利用者の方から質問されると、その分、図書館の蓄積が増えるのでラッキーだと思っています(笑)」。ここに、『図書館は市民と本・情報を結ぶ』(勁草書房、二〇一五年三月)所收の小林昌樹「「参照」してもらうのがレファレンス・サービス――インダイレクトこそサービスの本態」を讀み合はせれば――就中、その「2.2 「高度レファレンス」は課金が必要か?」で他ならぬ大阪府立圖書館が事例であったことに鑑みれば――、なかなかに意味深。
http://www.nakanoshima-univ.com/about/tomin/
http://www.nakanoshima-univ.com/pdf/tomin_vol82.pdf
http://blog.goo.ne.jp/hanul-palam/e/8d762f90c872bd4999571c949de29a8f