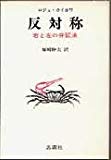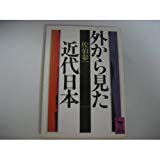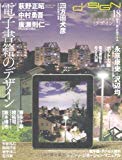[投稿日] 2010-11-30
年: 2010年(227件)
▼日本の遊戯 (1950年)
[投稿日] 2010-11-29
一九四三年初版。五十音順事典形式。
▼反対称―右と左の弁証法 (1976年)
[投稿日] 2010-11-29
▼児戯生涯―一読書人の七十年 (汲古選書 (15))
[投稿日] 2010-11-29
▼レヴィ=ストロース―構造 (現代思想の冒険者たち)
[投稿日] 2010-11-29
▼外から見た近代日本 (講談社学術文庫 (645))
[投稿日] 2010-11-25
初版副題「明治維新と南北戦争」が落とされた。
http://www.mori-atsushi.jp/i-086.html
▼文字の組み方―組版/見てわかる新常識
[投稿日] 2010-11-20
▼季刊d/sign デザイン no.18
[投稿日] 2010-11-20
http://www.ohtabooks.com/publish/2010/10/16000000.html
▼武藤山治と時事新報
[投稿日] 2010-11-17
1.kamiyam 【2010-11-17 18:49】 (削除)
これは、國民會館叢書版(http://www.kokuminkaikan.jp/publishing/index.html)と同一内容なんでしょうかね。ページ数はあまり変わらないようですが。ちなみに以前、図書館のご自由にお持ち帰りくださいコーナーに置いてあったのでパラパラと読みましたが、取り立てて面白くなかった印象だけが残っています。
2.森 【2010-11-18 0:41】 (削除)
古書展で國民會館叢書版を見たけど高くて見送ったのでメモ代りに登録したのです。國民會館叢書ってラインナップを見ただけでも通俗保守論客の顏觸れで期待できませんが、時事新報は社史の無い不幸な新聞社なので基礎文獻とせざるを得ません。註はそれなりに附いてゐたやうですから、文獻を手繰る絲口にはなるかな、と。『三田評論』二〇〇七年四月號「特集 時事新報125年」によれば形式上まだ社は存續してゐるのださうで、慶應の方で研究してくれるとよいのですが。慶應義塾大学法学部政治学科玉井清研究会から〈近代日本政治資料〉と題して戰前マスメディアに關するものばかり十餘點出てゐるやうですが、この教授邊り時事新報をやる氣は無いのでせうか。
3.kamiyam 【2010-11-18 2:29】 (削除)
国民会館のサイト上では在庫切れになっていないようですね。たしかに時事新報は基礎研究がほとんどされてないようだから、せめて文献探索の手助けになるものがほしいところです。慶應の玉井清氏、うーん、時事新報を書誌的にきちんと整理研究するという志向はなさそうな印象ですけど。むしろ可能性があるのは慶應義塾福澤研究センターあたりかなと思うけど、サイトを見る限りそういう計画はないみたいですね。今編纂中という『福沢諭吉辞典』より時事新報の研究をまとめてくれた方がありがたいのですが。
▼書影でたどる関西の出版100 明治・大正・昭和の珍本稀書
[投稿日] 2010-11-16
http://westedit.exblog.jp/
▼法哲学入門 (双書・BUL Basic University Library)
[投稿日] 2010-11-16
▼懐徳堂―18世紀日本の「徳」の諸相 (NEW HISTORY)
[投稿日] 2010-11-15
▼増田義一追懐録 (1950年)
[投稿日] 2010-11-07
▼明治百年問題―「明治百年祭」は国民になにを要求するか (1968年)
[投稿日] 2010-11-07
香内三郎寄稿。
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2989812
▼民俗学覚書 (1973年)
[投稿日] 2010-11-07
▼集合的記憶
[投稿日] 2010-11-07
▼表象の奈落―フィクションと思考の動体視力
[投稿日] 2010-11-01
收録文中、總じて新しい年代のは今一つ。古いのは初出で讀んでゐたものも少なくない。差し引き收穫と思へたのは新出の「エンマ・ボヴァリーとリチャード・ニクソン」となるが、これは既讀の『「赤」の誘惑』の變奏曲(いや前奏か)。
目次 http://www.seidosha.co.jp/index.php?%C9%BD%BE%DD%A4%CE%C6%E0%CD%EE
▼「いい文章」ってなんだ? 入試作文・小論文の思想 (ちくま新書)
[投稿日] 2010-10-21
▼戦後批評のメタヒストリー 近代を記憶する場
[投稿日] 2010-10-21
書名に言ふ「批評」がほぼ文藝批評でしかない。『季刊批評』→『批評空間』の近代批評史が文學以外に擴げたのが生かされてない。難癖をつけるやうだが、社會派の態度を示す割に文學に囚はれてゐるのは料簡が狹くないか。文藝批評と言っても同時代文學評でなく過去の作家作品を論じたものが主對象だから、畢竟これは文學史論だらう。それはそれで結構だが、但し學術的な文學史研究は除外されてゐる――さうすれば學界批判には手を出さずに濟むし? いや、所詮は近代文學研究なぞ文藝批評の影響下から自立できぬ似而非學問といふことか。そこに屬する著者自身の立場は如何に。
メタヒストリーと言ふだけあって、ところどころで成程と思ふ概觀はある。例へば、中村光夫(ら)が白樺派をうまく扱へなかった理由とか。いささか疑問だが、江藤淳パラダイムがそんなにも鞏固だったのか(少なくとも著者の世代にとっては)、とか。この著者の本では一番性に合ふ方かもしれぬ。
目次 https://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0236540/top.html
▼学問がわかる500冊〈Volume2〉
[投稿日] 2010-10-21