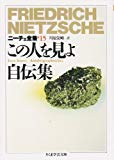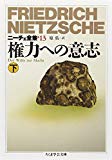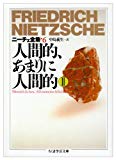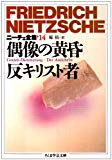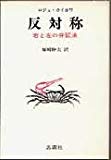[投稿日] 2010-09-01
▼ニーチェ全集〈13〉権力への意志 下 (ちくま学芸文庫)
[投稿日] 2010-09-01
▼ニーチェ全集〈6〉人間的、あまりに人間的 2 (ちくま学芸文庫)
[投稿日] 2010-09-01
▼悲劇の誕生―ニーチェ全集〈2〉 (ちくま学芸文庫)
[投稿日] 2010-12-26
▼ニーチェ全集〈14〉偶像の黄昏 反キリスト者 (ちくま学芸文庫)
[投稿日] 2010-12-26
▼読書人の没落―世紀末から第三帝国までのドイツ知識人
[投稿日] 2010-09-25
スチュアート・ヒューズのドイツ特化版(時代はやや古い)みたいなもので、讀み易い。例へば、Idealismが觀念論でなく理想主義といふ實踐倫理上の意味に解されてしまふ事情など、知られてゐることかもしれないが、ハッキリ説明した本を他に見た憶えがない。これ一卷でおよそ、ドイツの人文學者(延いては近代日本の教養主義者)の道學先生ぶり、空疎な政治志向(謂はば不純な非政治性、ex.p.74)の由って來る所以が呑み込める。マイネッケはあれでもましな方だったわけだ、著者の謂ふ「正統派」に比べれば。對する「近代派」の中でもマックス・ウェーバーだけ評價がやけに高く、確かに優れてゐたのは認めるにせよ、果して同時代にあってそんなにも孤立してゐたのかは不審である。また西村稔「訳者あとがき」は法學者があまり取り上げられてゐないことを指摘するが、法學にも史學にも範型を提供した文獻學(このことは數學史の佐々木力さへ特筆する所だ)への言及にも乏しい。フンボルト以來の新人文主義の理念が古典に親しむものであることから言っても、文獻學の檢討が求められる。ヴェルナー・イェーガーは何度か出てくるが……曽田長人『人文主義と国民形成 19世紀ドイツの古典教養』(知泉書館、二〇〇五年)に就くべきか。
ところで、大學知識人をmandarinsに喩へそれを「読書人」と譯すのはよいとして、では、大學の教育職に屬さぬのは勿論のこと、國民やら國家やらと無縁な逸民であり、端っから沒落してゐる「讀書人」の歴史は何の本で讀めばいいのかね? これほどまでにドイツ精神主義者どもの反面教師ぶりを見せつけられながら、なほも現代日本における「知識人の使命」を問ひ敢へて「精神」論を説く「訳者あとがき」は、悲壯な決意と言ふより士大夫を氣取りたがる大學人の度し難き頑迷さを感じさせる。
▼イメージの歴史―ザクスル講義選集
[投稿日] 2009-11-19
▼知の歴史社会学―フランスとドイツにおける教養1890~1920
[投稿日] 2010-09-26
副題にある「教養」よりは「教育」を論ずる。フランスの教育制度や教育改革について記述した前半は退屈。後半、第4章以降やうやく思想史らしくなってきて、ランソン、セニョーボス、デュルケームらの言説(專ら教育論だが)が紹介され考察されると興味が湧く。特に、歴史主義及びフランス史學史に關しては。しかしドイツとの對比はあまり成功してないと思ふ。
▼偶有からの哲学-技術と記憶と意識の話
[投稿日] 2009-11-26
▼ヘーゲル以後の歴史哲学―歴史主義と歴史的理性批判 (叢書・ウニベルシタス)
[投稿日] 2010-10-05
譯者(古東哲明)の〔 〕による補足が必要以上に多い。
卷末「文献表」に邦譯を補ってあるのは哲學書ばかり、マイネッケすら漏れてゐるってどういふこと?
その分析はなかなか讀解の參考になるものの所詮は哲學者の論、哲學史に限定されてをり、歴史家であるブルクハルトやドロイゼンの章を立ててゐるとはいへ、科學史(學問史)に及ばない。「歴史認識の実践〔暗黙裡の行為〕を哲学的に解釈することと、その歴史認識の実践自体との、事柄としては必然的なつきあわせ〔対比〕を、おこなわないままにとどめざるをえなかった。そうしたつきあわせ〔対比〕は、科学史家との共同作業をつうじてのみ、なされるべきだからである」(p.38)。これだから哲學者って……カッシーラーやフーコーの爪の垢でも煎じて飮め。
cf. 笠原賢介譯ヘルベルト・シュネーデルバッハ「歴史における‘意味’?――歴史主義の限界について――」http://hdl.handle.net/10114/3995
▼近代の精神 藝術的世界と科學的世界
[投稿日] 2016-07-09
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1038908?tocOpened=1
▼歴史主義の立場 (史学叢書) (1943年)
[投稿日] 2011-01-21
同じく中山治一譯の『歴史的感覚と歴史の意味』(〈創文社歴史学叢書〉一九七二年四月)と、いづれ對校すべし。
目次 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1041161
▼マックス・ウェーバー〈第1〉 (1963年)
[投稿日] 2010-08-31
一九八七年九月に合册一卷本が出てゐる。
http://www.msz.co.jp/book/detail/01949.html
▼マックス・ウェーバー〈第2〉 (1965年)
[投稿日] 2010-08-31
▼比較史の方法 (1978年) (歴史学叢書)
[投稿日] 2010-12-19
アントワーヌ・メイエ『史的言語学における比較の方法』を引いて比較に二種類あると概念分けしたところは、比較文學で論爭になった一般文學(廣義の比較文學)か比較文學(狹義)かといふ問題に相似する。しかし、比較文學はフランスが本場だったといふのに、ブロックは勿論ページ數の半ばを占める譯者解説も參照してない。逆に、比較文學論でメイエやブロックを引いたものも管見に入らない。またブロックが比較二種のうち前者についてフレイザー『金枝篇』を例に出してゐる通り、民俗學・人類學・神話學にとっても他人事ではない筈。カルロ・ギンズブルグ『闇の歴史 サバトの解読』に於るフォークロア的比較法の導入に伴ふ問題點は上村忠男『歴史家と母たち』の特に論ずるところであったが、あれもブロックは引證しても比較文學までは取り上げてない。惟ふに、言語・歴史・文學・民俗・生物學その他多領域に跨がった一般比較方法論が考へられてよい。といふか、誰か書いてゐてもよささうだが……これ以上、比較文學研究史とか調べるのは門外漢には面倒臭い。
▼贈与論 (ちくま学芸文庫)
[投稿日] 2009-10-29
▼隠喩・神話・事実性―ミハイル・ヤンポリスキー日本講演集
[投稿日] 2010-10-06
興味持って讀めたのは「文献学化――ラディカルな文献学のプロジェクト」(乗松亨平譯)のみ。ヴォルフに發する近代文獻學の歴史を顧みるに、シュライエルマッハー→ディルタイの解釋學に至る正統哲學路線に抗してフリードリヒ・シュレーゲル及びニーチェの非正統的な文獻學があったといふ見取圖で、刺戟的ではある。曰く、「哲学者たち」が「テクストを現在の必要に適合させる」ため「アレゴリー的解釈を発明し」た一方、文獻學者は「ロゴスの中継にのみ関わり意味には関与しない」(p.72)。「文献学が、理解する無理解という学問として興った」……「文献学がテクストの意味を理解しない学問として自己規定するのは」(「理解しない」に五字傍點)……「文献学は哲学により形成される。その分身として、理解[二字傍點]を希求する哲学に対する批判として、反省されざるものという哲学に不可欠の層に関する知として」(p.73)。ここでシュレーゲルの「無理解について」(山本定祐譯「難解ということについて」)のイロニー論を持ってくるのは、うまい。また「ロゴスの物質性」(p.73)の傳承を事とする、その意味での文獻學は、殆どメディア論に接近してゐる。でも最後にハイデガーなんかで締め括るのは勘辨な。それでは結局哲學になってしまふ。もっとラッハマンとかシュピッツァーとかアウエルバッハとか檢討すべき文獻學者が居るでせうが。
cf.http://members.at.infoseek.co.jp/studia_humanitatis/RhetoricabookIII.html
http://6728.teacup.com/humanitas/bbs/t2/l50
▼想像的なものの人間学
[投稿日] 2010-09-04
http://ehescbook.com/shoseki_shousai/souzou.html
▼グリム兄弟 メルヘン論集 (叢書・ウニベルシタス)
[投稿日] 2009-10-29
▼反対称―右と左の弁証法 (1976年)
[投稿日] 2010-11-29