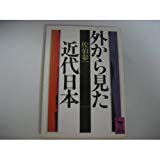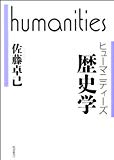[投稿日] 2010-09-04
▼遠野奇談
[投稿日] 2009-10-29
▼風雪新劇志―わが半生の記 (1959年)
[投稿日] 2011-01-08
▼(ブレインズ叢書1) 「批評」とは何か? 批評家養成ギブス
[投稿日] 2009-10-29
▼「スコットランド学派」における「文明社会」論の構成――‘natural history of civil society’の一考察――
[投稿日] 2015-12-21
同題「(一)」~「(四・完)」として『國家學會雜誌』八十五卷七・八號(一九七二年十一月)より八十六卷一・二號(一九七三年四月)まで四回連載の合綴、奧附刊記無し。拔刷でも使ったか。
http://ci.nii.ac.jp/naid/40001394224
http://ci.nii.ac.jp/naid/40001394229
http://ci.nii.ac.jp/naid/40001394231
http://ci.nii.ac.jp/naid/40001394235
紐栞まで附けた布裝ハードカバー。著者は丸山眞男門下にありがちな――實際は同じ東大法學部でも福田歡一門の由だが――寡筆且つ本出さない病の人らしく、それで斯く私に製本する需要もあったわけだらう。横にありし田中秀夫『ジョン・ミラー研究序説』(『甲南経済学論集』一九八二~八四年四回連載)も舊藏作製者同じかるべし、但しそちらは原紙ではなくコピーを綴ぢ込んでワープロで題扉を作ってあった。
元は一九七一年博士論文。
http://gazo.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gakui/cgi-bin/gazo.cgi?no=102423
http://ci.nii.ac.jp/naid/500000399445
「佐々木論文は重要な研究だと思いました。あれが出版されないままであるのはもったいないことです。彼に出版を勧めると、「あれは心ある人に読んでもらったらそれでよい」と素っ気ない返事をします」(田中秀夫『近代社会とは何か ケンブリッジ学派とスコットランド啓蒙』「第三章 自然法、共和主義、スコットランド啓蒙――水田文庫と私の研究――」京都大学學術出版会〈学術選書〉、二〇一三年七月、p.61)。
▼外から見た近代日本 (講談社学術文庫 (645))
[投稿日] 2010-11-25
初版副題「明治維新と南北戦争」が落とされた。
http://www.mori-atsushi.jp/i-086.html
▼書物の森へ 西洋の初期印刷本と版画
[投稿日] 2016-04-30
展覽會圖録、チケットとチラシの挾み込みあり。CiNiiに據れば「正誤表あり」だが見當らず。
山口昌男「木版画の中の異形者たち」
雪嶋宏一「ヨーロッパの初期印刷本」
松枝到「書物への熱い夢」
田辺幹之助「ドイツ初期印刷本の中の死の舞踏」
佐川美智子「書物の森へ――」
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BN15987213
▼歴史学 (ヒューマニティーズ)
[投稿日] 2011-03-26
余は如何にしてメディア史研究者となりしか、を綴る自傳的構成。その個別例を以て歴史學一般の問題にどこまで迫れたかが肝要だが……。すらすら直ぐに讀み了へられ達意の文である分だけ、あまり理論的考察に踏み込めないのは、この輕い叢書の性格上已むを得まい。
この本で論じ切れてない問題を引き取ると、著者が擧げる「宣伝」「公共性(圏)」「国民化」の接眼レンズ三點セットよりも重要なのは、「私はどれだけ大衆なのか」(p.71)といふ問ひと見た。大學大衆化に抗する「フンボルト理念」を創られた傳統と承知の上で信奉すると言ふが(p.10)、單なるエリート教養主義でなしに現在のマンモス大學や大學外の大衆社會でその理念は果して實踐し得るのか。享樂を好む大衆性は一面でアカデミズムに對するディレッタンティズム(pp.67-68)にも繋がるし、「社会史ブームは、[……]歴史学の印象を非政治的な雑学趣味にしてしまった」(p.29)といふ事態の底には歴史學徒さへももはや「政治的人間である「市民」」(p.29)から大衆に化したといふ社會状況があるのではないか。また世俗の垢に泥んだ大衆からすれば、鈴木庫三が「野蛮な軍人」ではなく「生真面目過ぎるほどの情熱」を持った「教育改革」の提唱者であったといふ發見(pp.87-88)は、鈴木を免罪するよりは寧ろそんな糞マジメだからこそ端迷惑な惡果を生じたといふ見方になるべきではないか。
「ひょっとするとディレッタントは誉め言葉だったのかもしれないが」(p.67)……否、蔑稱だったとしても、その價値判斷を逆轉すべきなのだ。佐藤卓己には、自分の長所がオモシロガリズムにあることを忘れないで貰ひたいものだ。
目次 http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0283220/top.html
▼国語学研究事典
[投稿日] 2012-06-07
▼戦後批評のメタヒストリー 近代を記憶する場
[投稿日] 2010-10-21
書名に言ふ「批評」がほぼ文藝批評でしかない。『季刊批評』→『批評空間』の近代批評史が文學以外に擴げたのが生かされてない。難癖をつけるやうだが、社會派の態度を示す割に文學に囚はれてゐるのは料簡が狹くないか。文藝批評と言っても同時代文學評でなく過去の作家作品を論じたものが主對象だから、畢竟これは文學史論だらう。それはそれで結構だが、但し學術的な文學史研究は除外されてゐる――さうすれば學界批判には手を出さずに濟むし? いや、所詮は近代文學研究なぞ文藝批評の影響下から自立できぬ似而非學問といふことか。そこに屬する著者自身の立場は如何に。
メタヒストリーと言ふだけあって、ところどころで成程と思ふ概觀はある。例へば、中村光夫(ら)が白樺派をうまく扱へなかった理由とか。いささか疑問だが、江藤淳パラダイムがそんなにも鞏固だったのか(少なくとも著者の世代にとっては)、とか。この著者の本では一番性に合ふ方かもしれぬ。
目次 https://www.iwanami.co.jp/moreinfo/0236540/top.html
▼日本人物月旦集成 相當なもの 登場人物四百六名
[投稿日] 2016-06-24
裸本。「はしがき」末に「編者しるす」とあれば著でなく編とすべきか。
書名で冠稱を「人物月旦」とのみ記し副題を「登場人物四百〇五名」と誤植した標題紙を持つ異版が國會圖書館の内交本にある。
http://id.ndl.go.jp/bib/000000757371
「此の四百六名は、昭和八年七月三十一日より九年十二月二十七日まで『帝都日日新聞』に掲載されたところのもので、人物それ自身に於いて何か動きがあつた時に際して、之を俎上に上せたものが過半數を占めてゐる。仍つてそれ以後に於いてその立場に變動を來した者に對してはそれをいちいち訂正せずに、多くは(追記)として言ふべき必要のある分だけは書き添へておいた」(「はしがき」)。
イロハ順。
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1916734?tocOpened=1
野依秀市の項あり、曰く「『帝都日日新聞紙』上に『相當なもの』欄を掲げるに當り、いかに何でも社長野依秀市を書く譯にはいかず、隔日に執筆せらるゝ三宅雪嶺先生すら差控へた程であるが、一卷に纏めるに際しては相當なものとして是非一枚加へない譯にいかぬ」(p.490)。
大屋幸世『蒐書日誌 一』に言及あり。
▼世界文豪讀本全集 ヴァレリイ篇
[投稿日] 2016-04-23
國會圖書館所藏無し。外函底面に「第十二回最終配本」と印字。複刻『世界文豪読本全集 第Ⅲ巻』(クレス出版、二〇〇一年)所收、クレス出版サイトには「月報付」とあるがそれは缺。但しこの卷の月報記事は再録のみ。
http://www.kress-jp.com/kress041.htm#book418
本體背文字と標題紙のみ「世界文豪讀本全集」の「全集」二字を略す。
http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA41075525
▼古書通例―中国文献学入門 (東洋文庫)
[投稿日] 2011-07-20
「一つの手がかりとして、中国の古書を論じる際にしばしば用いられる「形制」という概念を導入し、これを余嘉錫のいう「体例」に対置してみたい。両者はともに書物の内容よりも形式に着眼するものだが、前者が材料、形状、行格、書写方法等、主として技術的な側面を指すのに対し、後者が書名や撰者名、書物の構成や著述の習慣等、より実質的な側面を指すという違いがある。」(内山直樹「解説」p.355)
本書で古書とは前漢以前に竹簡や絹帛の卷子で傳へられた先秦諸子の古典なので餘りに縁遠く、對象そのものの興味は薄い。中文中國史專門でないと讀んでも仕方無いかも。ただ、書名・著者名・編次その他のあり方即ち「体例」から考證してゆくといふ方法は面白く、幾分かジェラール・ジュネット『スイユ』に通じ、フーコー「作者とは何か」からロジェ・シャルチエ『書物の秩序』が引き取った議論を想はせないでもない。ここに論じられた支那古代の書物と對照することで、蔡倫紙以降の我々の「書物」の既成概念を歴史的に相對化し改めて問ひ直す契機は得られよう。でも、支那人は古を求めるに專らだし、邦人の支那學徒も專門研究に沒頭して一般讀書人に訴へる所無く(『古書通例』の譯者ら然り)、日本や近代の書誌學と繋げるさういふことまでやってくれないんだよなあ……。
https://yujiaxi.wordpress.com/
▼目録学 (1979年) (東洋学文献センター叢刊影印版〈1〉)
[投稿日] 2011-04-29
章學誠『校讎通義』が讀みたくなる。
内藤湖南『支那目録學』からどの程度に踏襲しまた踏み出してゐるかを測らねばなるまい。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/iocpicservice/110330~%E5%80%89%E7%9F%B3%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88/05019~05019%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9B%AE%E9%8C%B2%E5%AD%A6/
↓
http://picservice.ioc.u-tokyo.ac.jp/01_130112~%E6%BC%A2%E7%B1%8D%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%BA%AB/110330~%E5%80%89%E7%9F%B3%E6%AD%A6%E5%9B%9B%E9%83%8E%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88/050190~050190%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%9B%AE%E9%8C%B2%E5%AD%B8/
▼校勘学講義―中国古典文献の読み方 (中国古典文献学・基礎篇 (1))
[投稿日] 2009-10-30
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~hidemi/pro04.html
▼上海漫語
[投稿日] 2014-12-29
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1872504/6
▼内田勇三郎 追想集
[投稿日] 2015-04-25
非賣品、編者は長男、歿後十年記念。挾み込みあり、内田純平編『『内田勇三郎追想集』執筆者の紹介』本文七ページ。國會圖書館・CiNii所藏無し。
内田・クレペリン作業檢査法で知られる心理學者。他に戸川行男・外岡豊彦・内田純平編『心理学者内田勇三郎のしごと』(日本・精神技術研究所、一九八三年)、内田純平『迷留辺荘主人あれやこれや 心理学者内田勇三郎の生き方の流儀』(近代文芸社、一九九五年)があるらしいが未見。
▼内田魯庵全集 別巻 雑纂
[投稿日] 2015-10-31
最終卷。挾み込み册子は「全巻目録」「正誤一覧」より成る。
酒鬼
當世文學通
紅葉山人の「拈華微笑」
讀小説法
當世作者懺悔
歳末最後の所感
藏書の趣味
二十世紀 質屋の車
百科全書の過去及現在
感じを現はす言葉
社會批評家としてのバアナアド、ショオを論ず
英國に於けるイブセン劇の編年書史
森鴎外論
明治の飜譯
ブランデスの讀書論
新希臘主義
移轉男
又玄夜談
語録趣味
落伍者也、失敗者也
強兵の幻滅
財産没収叩き放し
惡辣政治家の傀儡たる勿れ
余が愛讀の紀行
禁酒・節酒・小酌論の根據及び其批判
家賃は漸減すべし
小部落を作るのみ
私の趣味 私の家庭に於ける遊戯とその方法
罰金税
兒孫の爲に蓄財するの可否
歌舞伎座で見たい狂言
インカの古陶器を前にコレクションの定義を
説く魯庵氏
悲しむべき世の傾向
一番不足してゐる科學的興味
凧のウナリ
女は進歩した
諸名士の雑誌新年號觀
『文藝東西南北』 序
閲覽聽聞月録
茶代は輕きに失せず
私の此頃の生活
新著を閑却するは本當の讀書家に非ず
寫眞の話
興味深く讀んだもの
貧困時代は終始一轍
明治文藝展に就て
文化移植時代
此頃の日記
婦人に薦めたい書物
窓から眺める
手持無沙汰
我子の場合
書籍の話
進歩したと思ふこと退歩したと思ふこと
日記(一)~(七)
内田魯庵年譜 野村喬編
内田魯庵著述年譜 野村喬編
解題 野村喬
解説 野村喬
▼内藤湖南全集〈第12巻〉
[投稿日] 2011-07-08
佐村八郎『國書解題』を難ずる文は本卷『目睹書譚』中「野籟居讀書記」二(pp.69-71.)にて、谷澤永一も再三引く所なれど、これ即ち、湖南は鄭樵「校讎略」における解題法の論(『支那目録學』pp.416-417,「支那の書目に就いて」p.457)を應用せるものなりと覺えたり。『支那目録學』は冒頭に「かの佐村氏の「國書解題」などでも[……]解題の意味をなさぬ」云々と見え、また『支那史學史』「九 宋代に於ける史學の發展」中「七 鄭樵の通志」にも崇文總目の解題の冗を批判せる條を引きつつ「これなどは近頃出来る解題の中にもあてはまるものがあるであらう」(東洋文庫版p.316)と述ぶるは『國書解題』が念頭にありたるものの如し。
▼支那史学史〈2〉 (東洋文庫)
[投稿日] 2011-07-08
全體の三分の一を占める清代の記述が壓卷(『清朝史通論』の「経學」「史學及び文學」の章と併讀すべし)。新しい時代から遡って讀んでいった方が面白いかも。章學誠論が未成に終ったのは惜しい。
索引の間違ひと不足が少し氣になった。